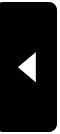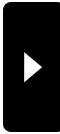› akicyanの 近江探訪記 › 藤井彦四郎邸で十二単着装イベント
› akicyanの 近江探訪記 › 藤井彦四郎邸で十二単着装イベント2019年04月09日
藤井彦四郎邸で十二単着装イベント
先月六日七日に、近江商人屋敷の“藤井彦四郎邸”で“隠れ里の雛灯り”というイベントがあり、十二単の着装鑑賞や雅楽の実演、キャンドルナイトなどが行われました。
他に子供さんへ向けてのイベントも行われていましたが、私は“十二単着装”“雅楽の実演”“キャンドルナイト”などを鑑賞させていただきました。
特に“十二単着装”に関しては先日も“商家に伝わるひな人形めぐり”イベントでも行われていましたが、その時は残念ながら他の用事と重なり見学できず、楽しみにしていました。
今回は十二単の着装を女流人形作家の「東之華さん」が詳しく説明してくださいました。

実演の模様です。



完成 素晴らしい!
参加者の方との写真撮影もしてくださいました。


着装の様子だけでなく、多くの着物は一本の帯でとめられているため、今着た着物をまとめて脱ぐ様子や、その着物がまとめて残った状態のものも見せていただきました。
十二単は俗称で、正式な名前は“五衣唐衣装”裳唐衣”などと呼ばれていたようですが、“もぬけの殻”という言葉は、ここらからきているようです。
また、脱いだ着物がまとめて残った様子を蝉のぬけがらになぞられ“空蝉”という言葉ができたようです。
十二単というものの、十二枚以下の場合もあれば十二枚以上の時もあり、身分や季節によっても色の合わせ方が変わるようです。



※写真は主催者に許可を得て撮影しています。
他に子供さんへ向けてのイベントも行われていましたが、私は“十二単着装”“雅楽の実演”“キャンドルナイト”などを鑑賞させていただきました。
特に“十二単着装”に関しては先日も“商家に伝わるひな人形めぐり”イベントでも行われていましたが、その時は残念ながら他の用事と重なり見学できず、楽しみにしていました。
今回は十二単の着装を女流人形作家の「東之華さん」が詳しく説明してくださいました。

実演の模様です。



完成 素晴らしい!
参加者の方との写真撮影もしてくださいました。


着装の様子だけでなく、多くの着物は一本の帯でとめられているため、今着た着物をまとめて脱ぐ様子や、その着物がまとめて残った状態のものも見せていただきました。
十二単は俗称で、正式な名前は“五衣唐衣装”裳唐衣”などと呼ばれていたようですが、“もぬけの殻”という言葉は、ここらからきているようです。
また、脱いだ着物がまとめて残った様子を蝉のぬけがらになぞられ“空蝉”という言葉ができたようです。
十二単というものの、十二枚以下の場合もあれば十二枚以上の時もあり、身分や季節によっても色の合わせ方が変わるようです。



※写真は主催者に許可を得て撮影しています。
Posted by Aki at 21:01│Comments(0)